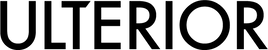15歳の頃に出会った生成りの染み込みプリントのビンテージスウェット。当時まだビンテージや洋服の知識も持たず、そのスウェットの価値すら分からなかったが、純粋に物の持つ魅力に目を奪われその場から離れることができなかった。どうしても手に入れたい強い衝動に駆られたが手持ちのお金も足りず、どうにか売って欲しいとそのスウェットの持ち主に懇願した。その人が条件に提示したのが、自分が今履いているハイテクスニーカーと交換することだった。まさかの展開にたじろぎながらも、その場でスニーカーを脱ぎ、代わりにそのスウェットを手にすることができた。商いの原点のようなこの物々交換の体験が、洋服を作る今の自分の出発点だったのだと気づくのはもっとずっと後になってからである。
学生時代は地元の小さなセレクトショップや古着屋に入り浸りながら服のこともそれ以外のことも教わる日々の中で、自分がどんどんと好きなものにのめり込んでいく感覚と、かつてスウェットを手にしたときの圧倒的な高揚感を頼り続け、気がついたときには洋服を自らの生業として選択していた。
生地が裂け、自分で補修し、シミがついても大切に着ていた自分の原点のスウェットは、もう着るに耐えない状態がゆえ大切に保管するだけになっているが、市場的価値がどうかなんて関係なく、この先もきっと捨てることはないだろう。 そんな個人的な思い入れもあり、ブランドをはじめてからずっと作り続けている裏毛シリーズは、どんなときもコレクションから外したことがない唯一のアイテムである。着続けて褪せた色も、薄くなった生地も、柔らかくなった肌触りも、年月が生み出した素晴らしい魅力だが、それをどう表現できるかということが、ブランドとしてずっと向き合い続ける課題なのだろう。原点は超えられないからこそ、そのルーツをどう解釈し、どう編集し、そしてどう表現するか。ブランドのアイデンティティはそこにしか存在しえないのではないだろうか。