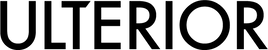擦れてくる生地、褪せてゆく色、ほつれる糸。服を長く着ると生まれるそんな変化を好ましく思えるのはなぜだろうか。きっとそこには、その服の着用者が過ごした時間が表れているからだろう。そこに見え隠れするストーリーに想いを馳せる時間は、愛おしさを生むものだ。
だからといって、時間を早送りしたような作為的な“経年”に対しては、同様の気持ちを抱くことは難しい。新しいものとしてこれから世に提案するものに対して、具体的なイメージや着地点を提示しては意味がないようにすら感じられる。そこにはやはり過ぎ去る時間の余白があるべきなのではなかろうか。
レモンイエローとも山吹色とも、鶯色ともダークグリーンともカーキとも呼べないような、間にある色。もとの色が退色していきかすれていったような名もなき色—。糸どうしの組み合わせや、素材の組み合わせ、織り、様々な要素を同時に試行錯誤しながら、目指したい色を作り上げていく。直接的な加工には可能な限り頼ることなく、新しさのなかに、新しいだけじゃないものを、古そうに見えるだけじゃないものを表現したい。その結果に生まれる色たちは新しく世に放たれ、そして誰かのもとにわたって、それぞれの時間を過ごしてまた変化していくものであって欲しい。